下駄はなおさんと、三木大雲上人の対談になります。
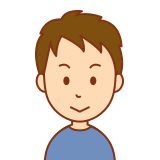
三木さん、気付いたんですよ。八十八カ所まわって、僕は何も知らない。心から本当に思って、お寺に行きます、ご住職とお話しします、いろいろ教えてもらって、他のお寺に行きます、そうなんですねと、またいろいろ教えてもらってばっかり。それがあって、自分も葬儀屋を以前やっていて、その中で三木さんはものすごく考えてらっしゃって。

お遍路をまわられて、案外、仏教って知らないなって思われるのは普通だと思うんです。むしろ、江戸時代とかその時代の人たちの方が、仏教に精通した人が多かったんですよ。何故かというと、娯楽がなかったので寺子屋で、親も一緒に行ってお坊さんの話を聞くのが娯楽の一つになっていたりしたので、結構、現代人の方が仏教を知らないと思います。
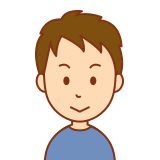
あー、確かにお遍路まわっていて、もと寺子屋というところがありました。

今回は寺子屋っぽく、お経に書いてあることは何なのっていう、驚愕のお経の中身を解説します。
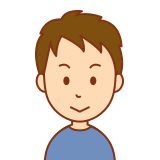
それではぜひ教えてください!

まずですね、お経というのは説かれた順番があるんです。まず、お釈迦様が一番最初に説かれたお経は華厳経なんですよ。華厳経というのを説くのは、今まで仏教のぶの字も
世の中にない所の、いわば数字でいうなら1,2,3というところの、「まずは最初に覚えましょうね」というのが華厳経。それから華厳経(けごん)、阿含経(あほん)、方等経(ほうとう)、般若経(はんにゃ)、法華経(ほっけ)、涅槃経(ねはん)の順番で説かれて行くんですよ。なぜ、この順番で説かれて行くかというと、1,2,3から教えて行って、1+1は2だよと言って、ずっとそういった説き方をして行くんです。それで、お経の経って糸遍に又書いて土ですよね。もともとはスートラっていうパーリー語で、どういう意味かというと「一本の糸」という意味なんです。要するに、華厳、阿含、方等、般若、法華、涅槃にいたるまで一本の糸でできている、お経は一本の糸でつながっているということなんです。ですから、究極の悟りを得ようと思ったら、華厳経から順番に勉強していかないといけないくらい大変なんです。
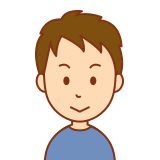
ということは、例えば般若経とはこうなんだよと悟るためには、華厳、阿含、方等から勉強していく必要ということなんですね。ある意味。

そうです。華厳経から勉強しましょうということになります。たぶん華厳経から勉強すると、年単位になります。すごく時間がかかります。華厳経から勉強するのは我々時間がないのですが、このお経のエキスをギュッと集めたお経があるんですよ。それさえしてれば、もう時間が無いので、これだけ覚えましょうというので、名前が「最上王経」といいます。最上でありお経の中の王様であるということです。「最上王経」は又の名を「法華経」といいます。これが「南無妙法蓮華経」を唱えるお経なんですけど、すごく分派がありまして、創価学会、顕正会、立正佼成会などなど。この法華経を唱えている教団は、実は日本の半分以上はこの法華経を唱えているんです。これが実は最上王経なんです。この法華経に書いてあるのが何なのかちょっと今回、少しだけお話させていただきたいと思います。
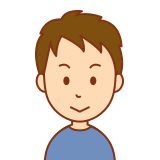
お願いします。

実は、法華経はすごい法則が説かれているんです。華厳、阿含、方等、般若、法華、涅槃と続きますが、法華で内容の毛色がすごく変わります。
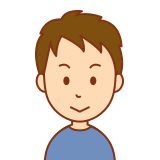
法華経になると、完全にジャンルが変わるということですか?

そうです。完全にジャンルが変わります。華厳経から般若経までは比較的心理学で、道徳的で、「正しく生きなさい」「正しく生きないと地獄におちる」といったことですが、ところが法華経以降で急に物理的な話になります。なぜかというと、精神が整っている人ではないと理解できないからです。妙法蓮華経ですけど、どういう意味かというと、妙は不可思議、法は法則です。不可思議な法則が説かれているんです。綺麗な言葉を発すれば、その人は運が開けると言うんです。なぜ私がそのような事を言うかというと、お経の中にそう書かれているんです。まず第一歩は「綺麗な言葉を使いましょうね」。それで綺麗な言葉を発すると、その人の運気が開けてくることも書いてあるんですけど、たとえば「笑う門には福来る」とありますけど、本当に笑っていたら福が来ます?
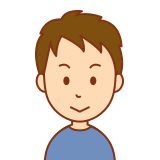
いや、笑ってたらなんでも福が来るっていう感じでは無いと思います。

騙される人もいたり、一見、不幸になる人もいたり。でも、過程において一旦騙されますよ、騙された後にこうしなさいということがお経の中に全部書いてあるんです。全部で法華経は8巻あるんですよ。28章に分かれているんですけど、この中に全ての不可思議の法則が説かれているんですよ。
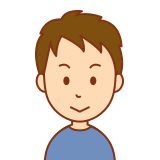
説かれているということは、ある意味、もう解決しているということですか?

そうです。解決しているということです。例えば、恋愛相談。「彼女に振られて今辛いんですけどどうしたらいいでしょうか」と相談されたら「ちょっと待ってくださいね」と法華経を見たら、そこにまた答えが書いてあるんです。要するに人生の解決方法が全て法華経に書いてあるんです。めちゃくちゃ不思議なんですよ。東洋医学に似ていますね。頭痛がするんですよと言ったら、足のツボを押したり。一見、全然関係ないと思うような事をすると、実はその悩みが解決するというような事が書かれていたり。人の為に何かをするという事は損をするんですよね。
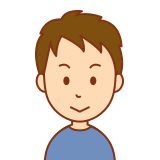
つまり、損をするとは、その人の為に何かをする事で、自分自身が何かを相手に与えるので何かを失うということですね。ある意味。

例えば、バスや電車に乗ってる時に、自分はとても疲れているのに他人に席をゆずるとしますよね。これはお経の中に「床座施」といいます。
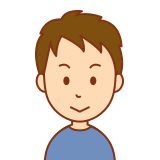
ちょっと待ってください。疲れた時に席を譲ることがお経の中に書いてあるんですか⁇

書いてあるんです。それを「床座施」と言うんです。人に席を譲る行為。それって得か損かで言うと、損ですよね。それはあなた方の目に見えている世界の物理学ですよとお経に書いてあるんです。一見損しますよ。でも、実は徳をしているんですと書いてあるんです。
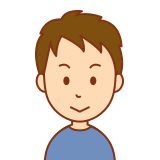
まさに、八十八カ所まわっていて、一番目にする字なんです。功徳を積むの「徳」ですね。

八十八か所めぐるということは疲れるんですよ。お金も使うんですよ。一つも「得」することが無いように思えるんですよ。物理的には。でも物理に見えない世界でいうと実は「徳」をどんどん貯めているんですよね。この「徳」というものを得るときに、自分一人が「徳」を得ているのではなくて、他の人にも「徳」を積ませているんですよ。これが何かというと、例えば「下駄さん、ジュースを飲んでください」と寄付をされますよね、これは「布施」という行為なんですけど、それによって他の人にも「徳」を積ませているんですよ。
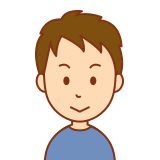
八十八か所巡りで、お接待してくれる方々がいて、あれはどうやらお接待することによって、自分も八十八カ所をまわっているということになるって言われてて、最初ピンとこなかったんですよ。ただ、お寺を巡って目をつぶってお経を唱える時に、自分に色々お世話をしてくれた方々の顔がぱーっと思い浮かんできて「あっ、この方々の分もまわっている」、そこで初めて気づいて。

それで、この「徳」を積むと実はもっといいことがありますよ、と山ほど説かれているんです。死後は「得」のほうは持って行けないんですよ。例えば下駄さんは今眼鏡をされていますけど、それは誰の眼鏡ですか?
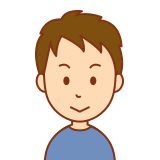
これは今、僕の眼鏡です。

下駄さんの眼鏡ですよね。下駄さんが亡くなられたら、そしたらその眼鏡は誰の物になるでしょう。下駄さんの物ではなくなりますよね。下駄さんが買われる前は所有者は違いますよね。つまり未来永劫の「得」は存在しないんですよ。死んでしまうまでの全てはレンタルなんですよ。ビデオを借りたら返さなくてはいけない、本を借りたら返さなくてはいけないのと一緒なんですよ。寿命というものがあって、この寿命の間だけ下駄さんの眼鏡なんです。借り物だから全ての物を大切にしなければならないんです。
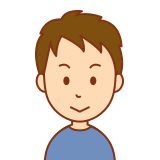
三木さんではなく、他のご住職から言われてハッとしたのは、皆さんは「命をいただいている」と言っていますけど、その方は「命をお借りしている」て言っていたんですよ。今、つながりました。

で、「この世はすべて仮の世界」というのがこの法華経に書かれているんですよ。なぜ仮の世界かというと、今私たちは絶対の約束ができないんですよ。例えば下駄さんと明日撮影を約束したとして、もし私が今晩死んでしまったら、撮影できないですよね。仮契約でしかないんですよ。絶対的な約束はできないんですよ。じゃあ何故仮の世界があるかというと、この「徳」と積ますためなんです。
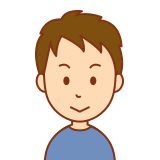
「徳を積むための仮の世界」

色んな良いことをさせるために私たちは今この世界に生きているんですよ。この真実を知った時に人生変わると思います。
後半へつづく・・・



コメント